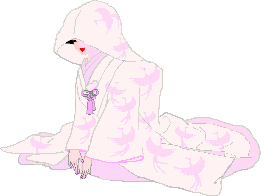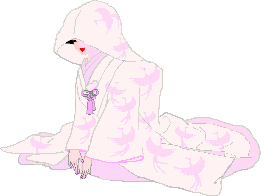|
あれは、親友の結婚式の日。久しぶりに思いっきりおしゃれをするか。22歳で結婚した私は子育てと仕事に追われ、もう何年もおしゃれをしたことがなかった。クローゼットの中から一番お気に入りのスーツを出し、離れて鏡の前に立った。ところが、いくら目をこらしても自分の姿をはっきり捕えることができなかった。『あれ、おかしいな、この鏡台は数日前に拭いたばかりなのに。』 不思議に思いながら、そばにあったティッシュをとり出し鏡を丁寧に拭いた。そして、もう一度鏡の前に立ってみたが結果は同じことだった。そこには、うすぼんやりと見える自分がいるだけ。『ま、まさか。そんなひどいことがある訳がない。昨日までは、きちんと見えていたじゃないか。』私の鼓動は一気に高なり、身も心もそのまま凍りついた。それは、鏡がほこっていたのではなく、我の瞳の中の鏡が壊れかけていたのだ。先天性の網膜症だった私の目は、知らずしらずの内に少しずつ悪くなっていたのだった。『これほど恐ろしいことが、他にあるのだろうか。』 いつか見えなくなるのだと覚悟はしていたが、あまりにも突然の出来事で、どうすればよいのか分からない。普段は洗面台や手鏡で顔だけを見ていた私は、『自分はまだ大丈夫だ』と信じていた。
その日は親友京子の結婚式。悪夢から逃げるように身支度を整え、急いで家を出た。そこは幸せいっぱいの彼女達、そして、あちこちから聞こえてくる楽しそうな笑い声も今の私を笑っているかのようだった。その場にいながら、私は嵐の後の濁流にすっぽり飲み込まれたようで、体はもちろん、指先一つ自由に動かせなかった。『これはつかの間の悪夢だ、子育てで疲れているんだ…。』と自分に言い聞かせた。それでもどうすればよいのか分からず、誰にも話すことができないまま数ヶ月が過ぎた。それからは、まるで学生時代の視力検査のように、『まだ隣の家が見えるだろうか、庭先のコスモスは…。』と不安ばかりが先に立ち、毎日朝の来るのが恐かった。それと、自分の目が悪くなったのを知られるのが悔しくて、いつも背伸びばかりしていた。それでも悲しい現実は、全速力で迫ってきた。いつも見てきた風景が、昨日も1つ、今日もまた1つ…と、目の前から消え心の思い出に変わって行く。そして、子どもの顔が完全に消えた時、『これは本当なんだ』と実感した。まだ、2人の子ども達は小、中学生で、この悲しい現実を話すことができなかった。気がついていないだろう夫にも言い出せないまま、わざとはしゃいで見せた。しかし、心の中は穏やかではなく、『見えないことは恥ずかしい、世界で一番不幸だ、もう死んでしまいたい…。』と思う反面、失明してほっとしてもいた。それは、いつ見えなくなるのだろうかという気持ちが怖かった。私の目は、わずか2年で全ての風景が消えた。それでも家族の前では強がり続けた。そして、一人になれば自然と涙が出て止まらない日々が続いていたある日、役所から白杖と点字板が送られてきた。それを手にした私は白杖を伸ばし、足に思いっきり力を入れて折った。なぜなら、見えないことが恥ずかしかった。不幸だとずっと思っていた。それに、惨めさを感じてもいた。これまで大きな挫折を感じたことがなかった私は、白杖に抵抗があった。そして、
「飾りの目などいらない」
と折れた白杖で目を突き刺した。的が外れ、眉間から鉄の臭いが鼻の中に入った。泣いた、暴れた、食器を投げつけた。頭では分かっていた。それを感情が受け入れてくれない。私は、公営団地に住んでいる。団地の人は声をそろえて、
「ここは、いつもねぶっても(なめても)もかまんように、きちんとしちょうねえ。」
と言われていた。そう、私は中途半端が大嫌いだった。愚痴を言う人は愚か者とさえ思っていた。投げつけた食器や折った白杖を一つひとつ片付けていたら、なぜか気持ちが少し落ちついたのは、感情の中で何かが変わったのだ。それは、たぶん現実から逃げることはできないということだったに違いない。その日からずっと何もなかったようにしていたつもりが、ある日、突然ピアノに頭をぶつけた時、『あぁ、そうだ、うちにもピアノがあったんだ。テレビも冷蔵庫もあるんじゃないか、それに夫も可愛い子供達もいるんだ。』と、忘れていたように気がついた。いつもはしゃいでいた私は、大きな森で立ち枯れしている木のように、ただ回りに支えられて立っている枯れ木そのものだった。『そうだ、何も変わらない暮らしがあるんじゃないか。』 そう思えば思うほど、『何も見えない私に、一体何ができるのだろうか。』と落ち込む日々が続いた。多くの人はこう言う、
「障害は不幸ではなく個性だ」
と。自身の考え方で否定することはできないが、自分はそう思うことができなかった。これからも、その考え方は変わらない。目が見えないで生きて行くこと、それは個性といえるほど単純なことではない。見えることが、どんなに便利で幸せか。かと言って、日々の暮らし全てが不幸の塊だということではない。
その晩も、また眠れないままに、ふと空を見た。そこは、これからの私の人生そのもののように、星一つ見えない真っ暗な空だった。ラジオでは、交通事故で歩けなくなった男の人がゲストに来ていた。それほど興味もないままに聴いていると、
「私二回赤ちゃんしているんですよ。長い人生ではありませんか、ゆっくり行きましょうよ。」
と言うのが聴こえてきた。『えっ、2回赤ちゃんしてるって?』 私は、しばらく狐につままれたような気持ちだったが、『そうか、そうか、また赤ちゃんになったと思えばよいんだな。それなら、今の私にもできそうだ。』 その瞬間、今までの例えようのない恐怖が、葉っぱについた朝のしずくのように、ぐるっと大きく回りすっと落ちた。『赤ちゃんなら何もできないことが当たり前で、何も恥かしいことではない。』 これからは、あせることなく、一歩ずつ進んで行けばよいんだ。その時、これからの我が人生に自らエールを贈った。
『よし、まずは読み書きができるようになろう。さあ、明日からは点字の猛特訓だ。』点字が少しずつ分るようになった私は、『人はガラス玉のようにもろく、石のように強いものだなと。』 そして、考え方一つで人生感が変ることを実感した。それからの私の人生は、最初は読み書きをするための点字、次はパソコンができるようになり、三歩めには、すばらしい盲導犬バーベリーとの出会い。そして、ようやく社会の中に四歩めをふみ出した。
それから10年が過ぎた。ある日の夏のこと。『今は こんなに悲しくて 涙も枯れはてて もう 二度と笑顔にはなれそうにないけど』で始まり、『あんな時代もあったねと きっと笑って話せるわ』というフレーズの『時代』という歌が、徳永英明のボーカリストの初っ端から聴こえてきた。とても聴くことなどできなかった。当時、事業所の代表、学校での講演会、高校の福祉の授業、パソコンボランティア、そして、家でのテープ起こしの仕事。昼夜を問わず自分なりに充実していた。事業所は、まだテレワークが一般的に知られていなかった時代、県内でも一早くそれらを可能にしていた。自分はその事業所の代表として『鉄の女』と言われるくらいスタッフには厳しかった。それは、半年ほどサポートに来てくれていたit関係の人に
「あなたは見えないのだから8割の出来でいいですよ。」
と言われたことが、頭にカチンときた。『8割の出来なら報酬も8割だ』と言うのならまだ話も分かる。それが、
「8割のできで人波に払います。」と言うのに惨めさを感じた。それがきっかけで、自分は代表として鉄の女になった。スタッフには、
「障碍者としての仕事はするな。」
と口癖のように言い続けた。さらに、
「納期は長めにとるから、完成度の高い商品を上げてくれ。」
と付け加えもした。スタッフは皆どこかに障害を抱えていたが、自分たちは『最先端を走っている』という自負が力をくれた。それからは、いろいろな資格もとり、大きなプロジェクトを抱え充実していたある日のこと。突然、『食べられない、眠れない、やる気が出ない、生きている意味がない…。』 ないないづくしの状態になり、医師から告げられた病名は、燃え尽き症候群からきた『強度のうつ病』だった。病名を告げられた時には驚く気力もなく、ただただぼんやりと遠くを見ていたが、次々に襲いかかる苦しみと悲しみ。そして、『何で、なぜ、どうして…。』 周りの人は、
「考え方次第よ、悩みのない者はいない、神経よ、それは更年期よ…。」
と、好きかってを言った。中でも身内から、
「病気がお前でよかった。これが亭主だったら困るがやった。」
と言われた時には、やっぱり、自分はここでは他人なんだと落ち込み、心身ともども燃えかすのようになってしまった。その上収入は減り、自身も仕事ができなくなり、経済的、精神的にも追い込まれ、行き場を失い、がぶりと沼地に引きずり込まれたような気になり、どん底をはい回ることしかできなかった。
ベッドに入り休んでいたある日、田んぼの畦道を行列をなして歩いている人の中に、親鸞聖人が見えたり、自分が一人で墓地に上がっているのが見えたりもした。夢ではない。確かに目は覚めている。目の前に現れた現象を思い出してみた。あの時親鸞証人は、なぜ泣いていたのだろうか。義父は坊さんをしていた。日常的に聞かされていたことが、そう、それは自分の気持ちの現れだったのだろう。心が完全に死んでいた。いや、そうではない。自らが死を選んでいた。けがをしている訳でもないが体全体が痛い。起きているのか寝ているのかさえ分からない。私は行動に出た。シーツを皆白に変え、喪服を着て、ありったけのビールと眠剤を飲み、『さようなら』と書いて眠りについた。どれだけ眠っっていたのだろうか、
「起きたか」
と言う夫の声が聞こえたような気がして目を開けた。そう、今はそこそこの眠剤では致死量には至らない。知っていたはずが、その分別もつかなくなってしまっていた。それから数日は、体が眠りを欲していたのだろう。私は、滾々と眠り続けた。
うつ病と言われて週に一度の病院通いが数年続いた。『これではだめだな、何とかしなければ。』と思えば思うほど、相反する自分に苛立ち自らを責め、居場所をなくし、生きるすべまでも見失ったある日のこと。数日分のドッグフードと薬、ロープにありあわせの現金をリュックに詰め、行く当てもなく盲導犬にハーネスをつけようとした時、今まで一度もなめたことがなかった彼女が、涙でぬらした私の頬をペロリとなめた。身体の中に熱いものが走り、我にかえった私は彼女を抱きしめいつまでも泣き続けた。そして彼女もまた、思いっきり体を寄せ私の背中にぐるりと前足をかけた。『そうだ、自分には大切なパートナーがいたんだ。これまで支えてくれた彼女がいるんだ。1人ではないんだ。』と、さらに、きつくきつく抱きしめた。
そして、娘が結婚した。式場に来た娘を見て、
「きれいやねえ。お母さんに見せちゃりたいに、見えんけん可哀そうに。」
と、皆が口をそろえた。その人たちには悪気は決してない。正直私も娘の晴れ姿は見たかった。私は空想した。衣装合わせの時に聞いていた色やデザインを思い出し、自分だけの娘の晴れ姿で良かった。そして親への手紙で、娘はこう締めくくった。
「お母さんに甘えたという記憶はあまりないけど、いつも温かく見守ってくれてありがとう。お母さんは、私のお手本です。」
と言うのを聞いて体が震え、涙が止まらなかった。横に立っている夫が、
「もう泣くなや」
と言うくらい泣いた。披露宴のことは、そのことしかほとんど覚えていない。それで良かった。心の中の晴れ姿と、娘の手紙で十分だった。娘は医療の専門家で、私の病気のことは知っていた。夫も十年余り精神科に努めていたので、いろいろな人を見てきたのだろう。いつも、穏やかに寄り添ってくれていた。
それから数か月後。激しい頭痛で気を失い、救急車の世話になり、気づくとICUのベッドの上だった。その時にもいろいろと検査をしてくれたらしいが、悪いところは特になかった。意識が戻り始めた時、ICUに一人残っていた息子が、私の額にそっと手のひらを当てた。たぶん、人前では恥ずかしくてできなかったのだろう。私は、それに気づかないふりをした。そして、家族のやさしさに自分の居場所があることを確信した。
それからは病院通いも月に一回になり、数年が立った頃、今度は目の前で光が暴れだし、心療内科から精神科に変えた。そこで告げられた病名は『シャルルポネ症候群(CBS)』だった。自分の症状をネットで調べ、主治医に自分から、
「CBSではないでしょうか?」
と問うた。主治医もきげんを悪くすることもなく、
「よくそこまで調べましたね。こちらも、それではないかと思っていました。」
という返事だった。私は、別の答えを期待していた。その病気なら治療法がないからだ。しかし、不思議と落ち込んだりすることはなかった。夫はこういう。
「自殺をしない限り、精神的な病気で死ぬことはない。」
と。私も、それは知っていた。今でも症状はひどく、疲れた時には床が岩のように盛り上がって迫ってくる。音にも光が反応し、早い音楽には光の暴れ方が激しい。頭の中で四六時中ぐるぐる回る。私は今年末で67歳になる。目の前の風景が消えてから30年近く、暗闇の中で生きてきたが、見えなくなって見えてきたものもあれば、失ったものも多かった。そして、今はこう思う。『悩むということは、決して悪いことではないと。何とかしたい、今を変えたいという前向きなことだなと。』さらに、こうも思う。『どうにかしようとする人は手段を探し、何もしたくない人は言い訳を探すと。』 そう、私は言い訳を探していたのかも知れない。できないことに「no」ばかり出してきたように思う。できたことに「OK」が出せなかったことが自身を苦しめてきた。30年という月日が、それを教えてくれたように思う。
そして、 私は歌った。そう、『時代』という歌を。今やっと笑って話せるようになった。思い出しても決して短くはなかった。だが、苦悩は永遠
には続かないのだと分かった。さらに、『壊れないものって何だろう』と考えてみた。私の答えは、それは『思い出』だった。死に行く時に、『良い人生だった』と思えるのは、終末期に高度な医療、意識がなくなる時に、いくらやさしい声をかけけ励ましても、それはもう遅い。生きてきた証は、その人の思い出に他ならない。人生は明日のことは分からない。だからこそ、今、この瞬間だけが保証されている。私は失明し、うつ病になり、先のことに絶望を感じ、健常者がうらやましく、惨めだと思ってきた。事業所の代表として肩ひじはり、同情されるのが腹立たしかった。それが、病気になり、
「気の性よ。考え方次第よ…。」
と突き放された時、本当は同情が欲しかったのかも知れない。失明した時、家族からの家事のサポートは全くなかった。当時は『少しは手伝ってくれればいいのに。冷たい家族だな。』と思った時期もあった。私は調理師と栄養学の資格をを持っている。一番苦労した毎日の食事作り。プライドもあり手伝ってよと言うことが言えなかった。工夫した。秤が分からない私は『手秤を考えた。そして、天ぷら油の温度も菜箸の振動で覚えた。そして『私の食生活の工夫』コンクールで『農林水産大臣彰』をもらった。その時、工夫に明け暮れた日々は無駄ではなかった。失明した時に、
「ガスは危ない、包丁は怖い…。」
と止められていたら、自分は家族のお荷物になっていただろう。自分が悩み工夫してこれたのは、手伝ってくれなかったことが、その時のリハビリになっていた。今は、そんな家族に感謝している。山あり谷ありの30年だったが、涙の数だけ得たものもあったのだと思う。今も社会人講師や高校の非常勤として授業を担当させてもらっている。講演会は、もう千回はこえただろう。その時に心がけていることが一つある。それは、『自分の言葉に嘘がないように』と言うこと。児童や生徒の前では、失明当時のことは話してもうつ病になったことは話さない。子ども達は、そんな話を期待などしていない。一番伝えたいことは、『悩むことは悪いことではないと思うよ。人として恥ずかしいことは何だろうね。そして、この世の中で絶対に壊れないものは思い出だとおもうよ。』と言うこと。講演会では、決して結論付けた話はしない。というより、何が正解で何が間違っているのかが分からない。一度口から出た言葉は、飲み込むことはできない。何気ない一言が、その人の人生を変える。それ程、言葉の力はすごい。これからも、自分の意志と行動。そして、我が言葉で社会に恩返しがしたいと思っている。
私は、時々思い出すことがある。それは、最後にみたあの群青色の海は、今も同じうなり声をあげているのだろうかと。いや、それは違う。大海原の営みも日々姿を変え、凪もあれば大暴れをすることもある。人生も、それに近いのかも知れない。私には、今も夢がある。それは、自分の人生を音楽で表現すること。歌詞はないが、自分で醸し出すピアノの音に、我が人生を重ねたいと思っている。
|