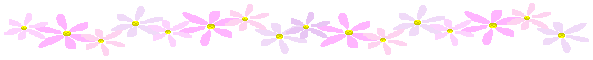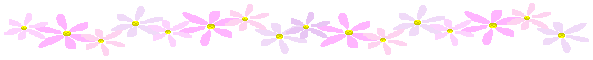|
「お父さんはかまわないが、親戚の者にも聞いてみないと…。」
これは、彼が結婚の申し込みをした時の父の返事だった。2年ほど前に連れ合いを亡くしていた父は、私達の結婚にそれほど強い反対はしていなかったが、心から賛成しているわけでもなかった。それは、
「なぜ、人がいやがる所へわざわざ行くがぞ。」
と言うことを、父は時々口にするようになっていたからだ。父はある宗教を信仰しており、人はどこで生れたのか、どんなことをしているのか…など、それほど気にも止めていなかった。それより、親戚関係がうるさくなるだろうと心配していた。
彼が結婚の話しをしてから数日後、予想通り私は父の強大によばれた。おじ達は全て関西に住んでおり、私は仕方なく出かけて行った。私自身それなりの覚悟はしていたが、それでもそこは想像がつかない悪夢だった。とにかく、私にはしゃべる隙を与えてくれなかった。それはもう、人としての最低の時間だった。
おじ達は私の気持ちを聞くこともせず、
「とにかく許さん。」と騒ぐだけだ。何がこうだから・こういうわけで許すことができないと言うのではなく、
「絶対ダメだ。」
と反対するばかりだ。私も、その時のおじ達の気持ちも分からないではなかった。それは、これまでずさんな人権教育を受けてきた者にとって、ある意味では仕方のないことだ。そのために、おじ達には差別しているという意識は全くない。それよりむしろ、親戚のために反対するのは当然だと思っているのだ。しかし、私はおじ達の説教を聞きにはるばる大阪まで来たのではない。彼との結婚の報告のために来たのだ。
ここに来て数日が過ぎようとしたある日、ほとほと説教に飽きてきた私は、
「おじさん達の言いたいことは十分分りました。今度は私の話も聞いて下さい。」
と切り出してみた。
「そうか・そうか分ったんかお前の言いたいことは何や。」
と言いながら、おじはタバコに火をつけた。
「私はおじさん達に結婚の相談をするために来たのではありません。彼と結婚することを報告するために来たんです。」
と言うと、その瞬間、なごんでいた空気は一変し、またまた言いたい放題の説教がはじまった。
人の固定観念というものは恐ろしいもので、私がすなおになれないこともおじ達は彼の性だと決めつけていた。おじ達の反対することの多くは、
「どうして人が嫌う所へわざわざ行くんや、同和地区という所は恐ろしいとこや、そんな所へ嫁がれるとこれから先の親戚の結婚に響くやないか、悪いことは言わんから、ここはお前のためにもあきらめた方がええんや…。」
などなど、珍しい反対の仕方ではなかったが、最終的には、
「宗教がちがう、名前の画数が合わない、方向が悪い…。」
などのように、ありとあらゆる理由をつけて反対した。
大阪に行って一週間近く、私はかごの中の鳥のように、買い物はおろか一歩も外に出ることが許されなかった。そのことがかえって、私に勇気を与えてくれたような気がした。毎日、毎日の説教にうんざりした私はこんな状態ではらちが明かないと思い、
「とにかく彼にあって下さい。」
とお願した。しばらくしておじが、
「よし会おうやないか。」
と言った。それまでの出来事が想像できなかったわけではなかったが、あまりにも醜いやり取りに、正直言ってある意味で人としてのおろかさを感じた。
夜勤明の彼が大阪に来たのは、それから二日後のことだった。私は空港に迎えに行き、それまでの状況を前もって彼に話した。これからの話し合いが、これ以上ややこしくならないためだ。私達がおじの家に着くと、親戚中が集っていた。私はどんなことを言われるのだろうかと気がきではなかったが、おじの第一声が、
「まあ、遠い所よう来てくれはったなあ。さあ、まあ一杯どうぞ。」
だったのには、正直言って驚いた。それからは彼に意見をするわけでもなく、飲めや歌えの大騒ぎだ。 私はその時、このにぎやかなその場に悲しい差別の現実を見た。それは、いかに部落の人を用心しているのかが、はっきり見てとれたからだ。今までおじ達が私に言ってきたことは、本来なら彼に言うべきことだ。なぜなら、
「人がいやがる所へは嫁にはやれん…。」
など、彼の方にはっきりと言うべきだ。それが彼を目の前にして何も言い出せなかったのは、おじ達の考えの中に、『部落の人は恐ろしいから…。』と言う意識があったからだ。本人を前にすると何も言えないのは、古くからのまちがった固定観念と偏見の性だ。これこそが、まさに差別の現実だと思った。
当時を思い出してみると、もし高校時代に同和問題との出会いがなければ、今の生活はなかっただろうし、一生同和問題と関ることなく、関係ないことだと無視して生きていたにちがいない。
結婚式には、父方の親戚は誰一人出席しなかったが、それでむしろ良かったんだと思った。結婚式は本人達の満足度の問題で、いやいや出席されても意味はない。当日は3月だというのに珍しく大雪が降り、昨日の雪が朝の大洋に照らされ銀色に光まぶしかった。私はすっかり支度ができ、門出するための客間に坐った。すると、母方の祖母が、
「お母さんが生きちょったらねえ…。」
と絶句した。私は昨夜からあれこれと父にする挨拶を考えていたが、とうとう言うことはなかった。それは、祖母の話しを聞いて、父が席をはずしたからだ。
母は一度も彼に会おうとしなかったが、亡くなる数日前にようやく会う約束をしてくれていた。その日は彼の仕事の都合がつかず、次の休日に会う約束をしたが、わずか数日後母は突然旅立ってしまった。母は回りが気がつかないまま、自分の死が近いのを感じていたのかも知れない。母との約束は今となっては守れないかも知れないが、あの時彼に会う気持ちになってくれたのは、許してくれるのだったにちがいないと信じている。
わが家では門出の艶が続いていたが、私は迎えのタクシーに乗り込んだ。彼の家とは10分も離れていないが、その日はどういうわけかやけに遠く感じた。わずか10分足らずの車の中で、今までのさまざまな出来事がせきを切った川のように…。何も考えなかった小学時代、病院通いも旅行気分だった。部活やサークルに没頭した中学時代。そして、彼や先輩に出会った高校時代。就職試験や進学、母との約束。そして、突然の母の旅立ち…など、まだ22年しか生きていないのに、もうずいぶん長く生きてきたような気がした。その時私はまだ大学の方へせきをおいていたが、これからの私の生き方を見守って下さいと、心の手を合わせた。
この間、わずか10分足らずの時間だったが、式場の前に車が止まり、その場に足を下ろした時、私は両手をきつく握りしめた。それは、数々の反対をおし切り自ら選んだこの人生に、後ろは振り向かないぞと誓ったからだ。やがて私達にも二人の子どもができ、平凡な暮らしの中で失明という現実が現れたのは、それから15年以上も先のことだった。
|